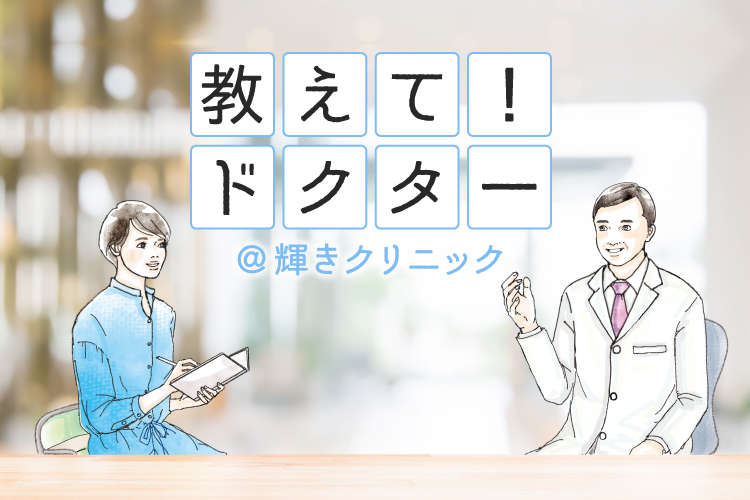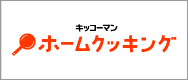イライラや不安を抱えがちな更年期。感情的になるのはどうして?
更新日: 公開日:
対策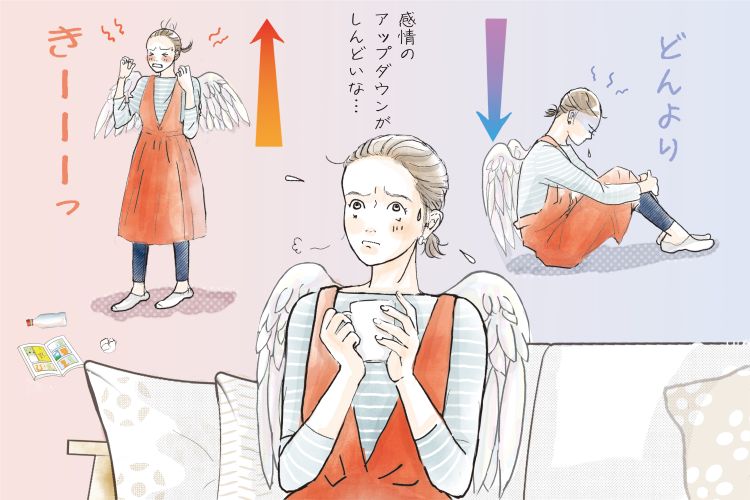

更年期世代のお悩みを、読者代表のヴィーナスたちが専門家に相談して解決する「お悩み解決隊」。今回は3人の子育てに大忙しのアイコが、日々感じるイライラや不安などの感情のコントロール法を、コーチング医の清水なほみ先生にお伺いしました。先生のアドバイスには、「認知のゆがみ」による考え方のクセを見直す方法や、更年期をよりよく過ごす工夫が盛りだくさんです!
更年期にイライラしやすくなる原因は、女性ホルモンの変化と「思考のクセ」
アイコ 先生、今日は私の感情についての悩みをご相談したいです。更年期になってから、すごくイライラしたかと思えば、後でそのことに落ち込んでしまうように、感情の振れ幅が大きくなってしまっている気がするんです。家族にも迷惑をかけている気がして…。どうしてこんなに感情が不安定になるんでしょう。
清水先生(以下、清水) アイコさん、それはお困りですね。更年期になると、女性ホルモン (卵胞ホルモン=エストロゲン)が急激に低下します。その影響で下垂体ホルモンが急増し、自律神経機能が乱れることがあります。そのせいかもしれませんね。
エストロゲンの低下は、脳や神経系に以下のように作用します。
●気分と感情
エストロゲンは、脳内のセロトニンやドーパミンなどの神経伝達物質のバランスを調整し、気分の安定に影響を与えています。そのため、エストロゲンが減少すると、うつ病や不安などの精神症状が引き起こされる可能性があります。
●自律神経系
エストロゲンは、自律神経系(交感神経と副交感神経)のバランスを調整し、心身のリラックスを促します。そのため、エストロゲンの減少は、自律神経の乱れを引き起こし、更年期障害の症状を悪化させる可能性があります。
●記憶と認知機能
エストロゲンは脳の記憶を司る、海馬におけるアセチルコリン(細胞同士の連絡を助ける神経伝達物質)の調整や、神経細胞の保護に役立つと考えられています。そのため、エストロゲンの減少は、記憶力の低下や認知症のリスク増加と関連する可能性があります。
アイコ もともと私が短気だから、更年期にイライラが強くなるのかなと思っていましたが、女性ホルモンの減少による更年期症状かもしれないんですね。更年期のイライラや抑うつ気分などの強弱は、その人自身の性格にもよるのでしょうか。
清水 そもそも、性格という明確なものがあるわけではなく、その人の思考のパターン(認知)による特性がどれだけ強く出ているかの違いなのです。
もともと抑うつ傾向の人がイライラしやすくなることもあれば、怒りっぽい人が、急にうつっぽくなることもあります。どちらかというと、自責傾向が強い人が抑うつ傾向になりやすく、他責傾向が強い人がイライラしやすいですね。また、楽観思考より、悲観思考の人が抑うつ傾向になりやすく、「全か無か思考」や「すべき思考」(後述)が強い人がイライラしやすいという傾向もあります。
もしアイコさんが、感情のゆれが特につらくて、仕事や人間関係などの日常生活に影響が出ていると感じるようであれば、治療を考えてもいいかもしれません。
アイコ 私の思考のパターンが問題かもしれないんですね。そんなこと、考えてもみませんでした。
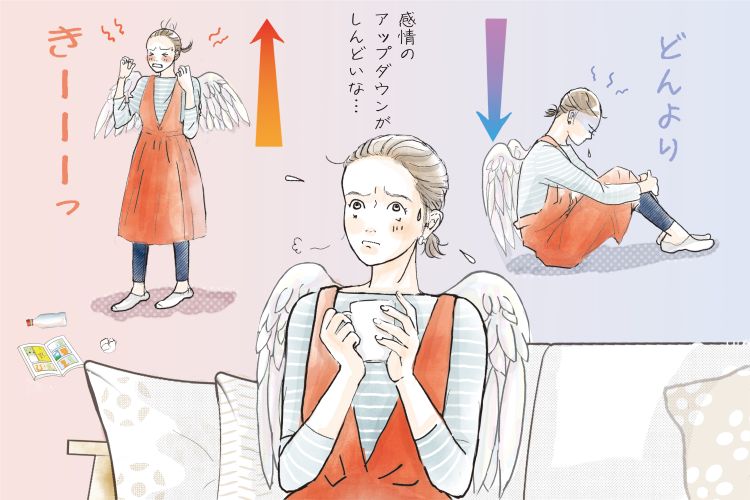
▶更年期に抱えがちな考え方のクセ、「認知のゆがみ」をチェックする
イライラ・不安が止まらないとき、心を整えるリセット術
アイコ 具体的にイライラや不安を覚えたときに、どうすれば心を安定させられるのでしょうか。
清水 では、イライラや心配、不安などの強い感情を感じたときに試してもらいたい対処法をお教えします。なお、順番に意味がありますので、できるだけ上から順に実践してみてください。
【イライラ、不安、心配を感じたときの対処法】
1)その感情が出てくることに許可を出します(そう感じる自分を受け入れましょう) 。
2)感情が強すぎて行動がコントロールできない場合は、安全な場所と人を選んで吐き出すといいでしょう。専門家のセッション(カウンセリング)を受けるか、「絶対否定してこない安全な人」に話を聞いてもらうのがおすすめです。
または、応急処置としてその感情を体のどこで感じるかを観察し、感情を「色・形・音」などの五感情報に例えた上で、その場所をイメージのなかで丹田(おへその下あたり)や足元に移動させてみてください。そして、五感情報がどう変化したかを観察します。
3)いったん冷静になれたら、どのような場面で何を感じたのか、感情が強く出た瞬間に浮かんだ考え(自動思考)を書き出してみましょう。さらに、それに対して「本当にそうだろうか?別の見方はできないだろうか?」と反対の視点を考え(反証)、それも書いておきましょう。
4)その反証のほかに、さらに別の考え方がないか探してみます。
5)その感情が自分に伝えようとしていることを読み取ります。
6)どのようなパターンでその感情を抱きやすいのかを見つけたら、今後のために、あらかじめ予防策(同じような感情を抱いたら、こう考えるといいという筋道)を立てておきましょう。
アイコ 感情を客観的に捉えるということなのでしょうか。私にできるかな…。
清水 そんなアイコさんには、私のアドバイスが有効だった具体的な例を1つご紹介しますね。
【感情を客観的に捉えるための具体例】
①椅子を二つ用意します。一つは自分用、もう一つは自分の感情用です。
②怒りや悲しみを自分の手のひらに取り出すイメージを持ちます。
③その感情に形を与え、擬人化してみます(どんな姿をしているか想像し観察しましょう)。
④一つの椅子に自分が座り、もう一つの椅子には擬人化した感情に座ってもらうと想像します。
⑤その感情と対話してみます。その感情が何のために産まれたのか、それによって何を伝えたいのかを聞き取り、それに対して返答してみてください。
⑥その感情からメッセージやアドバイスをもらいましょう。
⑦対話を終えたら、その感情をハグするイメージを持ちます。
⑧その感情を、自分のなかに戻してください。
アイコ なるほど!これなら具体的ですぐに試すことができそうです。今度カッとなってイライラが止まらなくなったとき、ぜひ行ってみたいと思います。

気持ちがゆれやすいのは「認知のゆがみ」のせいかも?10パターンをチェック!
アイコ 同年代の友人のなかには、更年期になって、私のように感情的になるタイプと、比較的感情が安定しているタイプがいるような気がします。この違いは何なのでしょうか?
清水 誰でも更年期によるうつやイライラが出る可能性はあるのですが…。
しいて言うなら、更年期に感情的になる人には、認知の偏りが強い傾向や、日頃から感情を自分のなかに溜めこみがちで、感情的に不安定になりやすいという傾向が見られることがあります。
なお、更年期に入って気持ちが安定したように見える人のなかには、月経周期の波がなくなった結果、ひどかったPMS(月経前症候群)やPMDD(月経前不快気分障害)が楽になってイライラが減ったというケースがあるかもしれません。また、年齢を重ねるうちに考え方が柔軟になり、自分の感情のコントロールが上手になって、徐々に感情が安定してきている可能性もありますね。
アイコ なるほど、そういう可能性があるんですね。ちなみに「認知の偏りが強い」というのはどういう意味でしょう。
清水 「認知の偏りが強い」というのは、別の言い方で「認知のゆがみ」ともいい、主に認知行動療法(認知のゆがみを客観視して、行動パターンを改善していく治療法)の現場で用いられる言葉です。同じ現象を見ても、それを「どう捉えるか」は人によって違いますよね。その捉え方が極端に偏っているときに「認知がゆがんでいる」と表現されます。「認知の偏り」の程度が強くなった状態が「認知のゆがみ」です。
これに関しては、具体例を示して説明したほうが分かりやすいかもしれませんね。感情に悪影響をおよぼす認知のゆがみパターン(心理学的学説に基づく)は主に以下の10パターンに分類されています。
【認知のゆがみ10パターン】
●認知のゆがみ パターン① 全か無か思考
白黒はっきりさせたがり、少しのミスでも「失敗」と決めつけます。完璧を求めすぎて自分や他人を責めがちになります。
●認知のゆがみ パターン② 一般化のしすぎ
一度の失敗や出来事を「いつも」「絶対」と拡大解釈してしまいます。根拠がなくても悪いパターンを予測してそうなると信じ込んでしまいます。
●認知のゆがみ パターン③ 心のフィルター
悪いことばかりに意識が向き、良いことや成功を見逃してしまいます。ネガティブな情報だけを拾って気分が沈みます。
●認知のゆがみ パターン④ マイナス化思考
褒められても「たまたま」と思い、素直に受け取れません。良い出来事ですら裏を読んでマイナスに捉えるため、自分の価値に結びつけられません。
●認知のゆがみ パターン⑤ 結論の飛躍
根拠のないストーリーを自動的に作り、不安な未来を想像します。相手の考えを勝手に解釈してネガティブになります。
●認知のゆがみ パターン⑥ 拡大解釈&過小評価
失敗や短所は大げさに捉え、成功や長所は小さく見積もってしまいます。自己評価がどんどん下がりやすくなります。
●認知のゆがみ パターン⑦ 感情的決めつけ
「不安だから無理」「落ち込むから価値がない」と感情で判断します。事実よりも気分に左右されやすい傾向です。
●認知のゆがみ パターン⑧ すべき思考
「〜すべき」と決めつけ、できない自分や他人を責めてしまいます。義務感が強すぎて心が苦しくなりがちです。
●認知のゆがみ パターン⑨ レッテル貼り
一度の出来事で「私はダメ」「あの人は最悪」と決めつけます。変化や成長の可能性を見失ってしまいやすいです。
●認知のゆがみ パターン⑩ 個人化
周囲の出来事をすべて自分のせいだと思い込み、必要以上に自責します。他人の感情や行動と自分を線引きできず背負いすぎてしまいます。

清水 認知のゆがみは誰でも起こりうるもので、認知がゆがむ原因として、「自己認識(自分自身をどのような人だと捉えているか)」と「信念価値観」が挙げられます。自己認識と信念価値観は、主に幼少期から自分がどう扱われてきたかやどういう情報に触れてきたかによって構築されるため、養父母や養育環境、成長過程で起きた大きな出来事(ショックな出来事)などの影響が大きく出がちです。なかでも特に、愛着形成障害(乳幼少期に、母親や父親との愛着形成がうまくいかず、問題を抱えていること)が起きやすい環境下にいた場合や、親自身の認知のゆがみが強い場合に発生しやすいといえます。
例えば、上司から「君、もっと頑張れよ」と言われたとき、“自分はできる人間だ”という自己認識を持っている人は、「自分は期待されている!もっと成果が出せるはずだと言われた!」と捉えますが、“自分はダメな人間だ”という自己認識を持っている人は、「また怒られた」と捉えます。
認知のゆがみとは「どのような色眼鏡を通して世界を見ているか」とも言い換えられます。認知のゆがみがあると、せっかくのきれいな景色を見ても、素直に「きれい」と感じることができないという悪影響が生まれてしまうのです。
アイコ なるほど、いくつかのパターンが私にも当てはまるような気がします。これは改善したほうがいいんですよね。
清水 いえ、認知のゆがみがあるからといって、必ずしも直す必要はありません。それによって社会的に不具合が発生しているなら(本人が困っているなら)、改善した方が良いということですね。
合わない眼鏡をかけていたとしても、よほど見えづらくならないと、それに気づけないことがありますよね。それと同じように、自分自身の認知のゆがみに気付けないことも多いので、「なんでこんなに生きづらいんだろう」とか「なんで自分だけいつも損をするんだろう」と感じたときに、自分のものの見方(認知)を見直してみるといいと思います。
ただ、もし自分の認知が気になるようでしたら、以下のことを試してみてください。
【認知のゆがみの改善方法】
●自分の思考のクセや、瞬間的に浮かぶ考え(自動思考)を客観的に捉えて書き出してみましょう。
●同じシチュエーションで他の人がどう捉えているのかを聞き、視野を広げてみましょう。
●認知行動療法を受けてみましょう。
そのつらさ、どこに相談すればいい?感情のゆれとクリニック選び
アイコ 更年期の感情のゆれもあり、認知のゆがみもある…。更年期の感情の動きって複雑なんですね。もし感情のコントロールのしにくさを感じたら、どんなタイミングで、どの科を受診すればいいのでしょうか。先ほど教えていただいた認知行動療法についても、もう少し教えていただきたいです。
清水 受診のタイミングは「いつもの自分が保てない」「少しつらい」くらいで早めがベターです。どの科に行ったらいいか分からない場合は、婦人科か女性総合診療科へ。メンタル症状を診てほしいと感じた場合は心療内科に行ってみてください。
婦人科では、ホルモン検査や必要な血液検査を行い、他の疾患を除外した後で、本人のリスクと希望を踏まえて治療に入ります。治療法としては、ホルモン補充療法、漢方・自律神経調整薬の処方・プラセンタ注射などの対症療法を選択することになります。メンタル症状がメインなら、カウンセリングも同時に行うと良いでしょう。
更年期によるホルモンの変化が原因であれば、ホットフラッシュや関節痛、軽い感情の波などは、1〜2カ月で7〜8割の方が改善しています。その一方で、なんとなくだるい・寝つきが悪い・頭痛・肩こりといった不定愁訴は、ホルモン補充をしても完全に改善しない方が半分ほどでしょうか。ただし、原因が夫婦関係のストレス(いわゆる“夫源病”)などの場合は、投薬治療だけでは改善しきらないことも多く、最終的に人間関係の見直しのような環境整備が必要になります。
なお、精神的なつらさは年齢に関係なく起こるものなので、「更年期症状」だと思って受診したものの「ホルモン値をみると更年期症状ではないですね」と言われる可能性はあります。
一方、認知行動療法を受けたい場合は、心療内科などのクリニック・カウンセリングルームや、個人のカウンセラーを頼ってください。認知行動療法は、心理カウンセリングよりも問題解決に直結しやすいというメリットがあります。
最近は、ICBT(インターネット認知行動療法)といって、アプリなどを使って自宅で受けられる治療法も広がっています。職場でのちょっとした悩みや、育児中のイライラ、くらいであればアプリでもある程度役に立つかと思われますが、複雑な問題の場合はインターネットではなく、直接クリニックを訪れることをおすすめします。
イライラしがちな更年期におすすめの、“暮らしの工夫”
アイコ 毎日の感情のゆれが気になりすぎたらクリニックに行くとして、もし他にも日々の生活のなかで気を付けるといいことがあれば教えていただきたいです。
清水 分かりました。それでは、感情がゆれがちな更年期世代に、日頃から気をつけていただきたいライフスタイルのポイントをお伝えしましょう。
【更年期に整えたいライフスタイル】
●食事面の工夫
・糖質を完全に制限するのではなく、血糖値の急上昇(血糖スパイク)を避ける食べ方を意識しましょう(血糖値が上がりにくい食品を選ぶ、野菜から先に食べる、よく噛んでゆっくり時間をかけて食べる、など)。
・鉄分や亜鉛を十分摂りましょう。
・カルシウムとマグネシウムをセットで摂るようにしましょう。
・夕食は早めに摂りましょう。
●入浴やリラクゼーション
・寝る90分前までに、シャワーではなくゆっくりと入浴しましょう。入浴はぬるめのお湯にゆっくり浸かるとベター。
・アロマを導入してみましょう(香りはお好みで)。
●睡眠の質の向上
・睡眠環境(明るさや音、室温など)を整えましょう。
・寝る前に漸進的筋弛緩法(ぜんしんてききんしかんほう・意識的に筋肉を緊張させ、その後脱力することで、全身をリラックスさせる方法)を行ってみましょう。
●運動
・朝の散歩、昼間に筋肉運動を伴う運動をしてみましょう。特に、自分が心地良いと感じる強度で、週3回程度コンスタントに運動することがおすすめです。
・最も重要なのは、運動「しなければならない」という気持ちから行うのではなく、運動「したい」という気持ちで行うことです。
●趣味などの時間
・社交的なら集団で行う体を動かすような趣味を。社交的でないなら、ガーデニングやクラフトなど一人で時間を忘れて黙々とできる趣味がおすすめです。
・食べることを趣味にすると、体重が増えやすい更年期には注意が必要です。できれば他の趣味を探すと良いでしょう。
アイコ ありがとうございます!特に趣味の部分は、私も何か新しいことをしたいなと思っているタイミングだったので、とても参考になります。ついついグルメを趣味にするところでした(笑)。
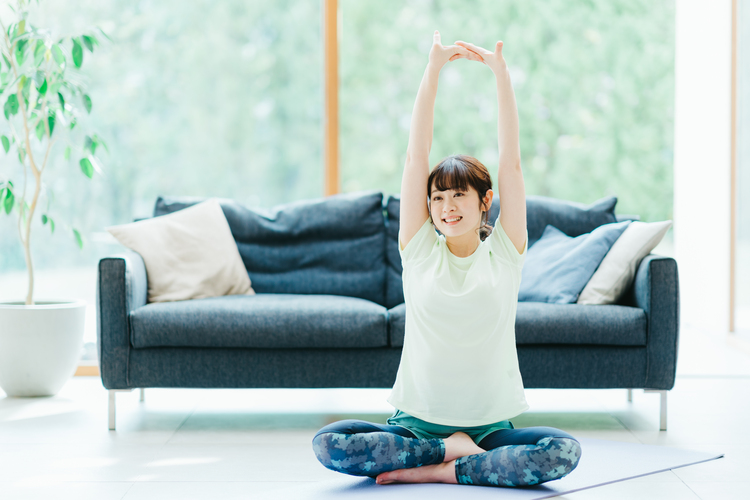
更年期は人生を折り返して少し。人生を見つめ直し、未来へ歩き出そう
アイコ 更年期に入って、自分の感情のゆれが本当につらかったので、今日のお話はとても参考になりました。今から感情面の対策は、今後の人生にも必要なことなんですね。
清水 “感情面”に限らず、不調が出たときには、「なぜこの不調が現れたのか」「何を教えてくれているのか」を見つめ直してみてください。人と同じ不調であっても、体が伝えようとしているメッセージは人によって異なります。ときには、自分が進みたい道から少しずれているサインを示しているかもしれません。早めに気づくことで、軌道修正も可能になります。
更年期の時期は、人生を折り返して少しの地点であり、「今やり直せば残りの人生に間に合う」時期。これまでの生き方、これからの生き方、人生の目的などを棚卸しして歩き直すのにちょうど良いタイミングなのですから。
アイコ 「今やり直せば残りの人生に間に合う」…。この言葉、すごく胸に響きます。私は、日々慌ただしく過ごすなかで、感情的になりやすくていつも反省ばかりだったので…。
清水 感情は必要があってわいてくるものなので、無理に「安定させよう」とする必要はありません。泣きわめいている子どもと同じようなものです。無理に抑え込もうとすると、かえって苦しくなってしまいます。まずは生まれた感情を受け止めて、その声を聴いて、どうしたいのかを自分の胸に問いかければ、自然に安定していくものです。ぜひ、上手な自分との付き合い方を見つけてください。
アイコ ううっ(涙)。分かりました、まず自分の感情を受け止めること、ですね。イライラや不安を感じたら、まずは自分の感情を客観的に見つめるところから始めてみようと思います。先生、今日はありがとうございました!
<この記事を監修いただいた先生>

清水 なほみ 先生
ポートサイド女性総合クリニック ビバリータ 院長
▼詳しいプロフィールを見る

アイコ
43歳。夫と小学生~中学生の子ども3人の5人家族。子育てをしながらパート勤務をこなし、毎日忙しく過ごしている。2年前からホットフラッシュやイライラ、不安感、気分の落ち込みに悩む。最近では、物忘れや高血圧、白髪、抜け毛の症状も。