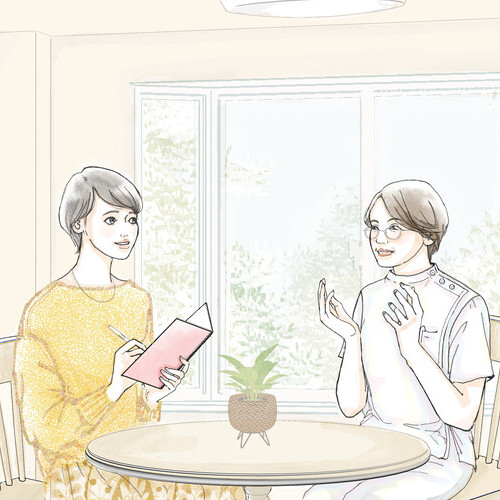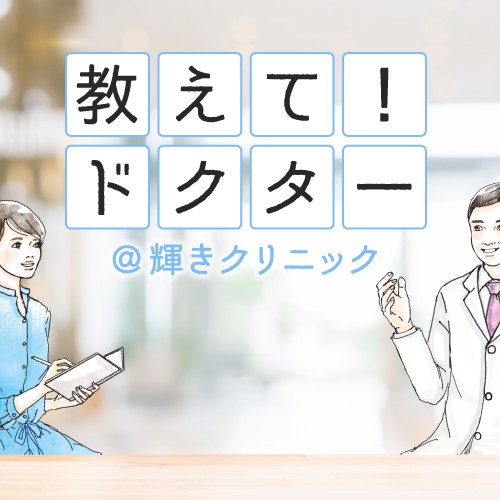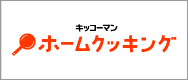更年期の口の乾燥について~適切なケアで口腔内の健康を保ちましょう~
更新日: 公開日:
学ぶ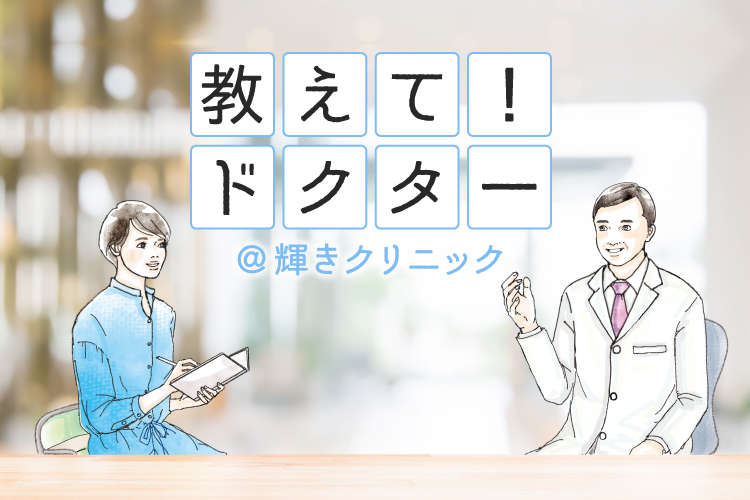
更年期を迎えて、口の乾燥が気になる人は少なくないようです。唾液が減ると虫歯や歯周病、口臭などにつながるほか、口の乾燥のかげにストレスや病気が隠れていることもあります。また、近年は、歯周病菌が、体全体に影響することも分かってきました。そこで今回は、「更年期の口腔内環境」について、更年期の専門医である東京科学大学(旧東京医科歯科大学)の寺内公一先生にお話を伺いました。
更年期以降、口の乾燥を実感しやすくなります
ー更年期を迎えて、口が乾燥しやすくなったと感じる人は少なくないようです。
寺内先生(以下、寺内) はい。当院の更年期外来を受診されている患者さんにおいても、「口の乾燥」を訴えられる方は多いと思います。
唾液の分泌量が減り、口の乾燥が続くことをドライマウス(口腔乾燥症)といいます。ドライマウスになる原因は一つではなく、さまざまな要因がありますが、加齢や口の周りにある筋肉の衰え(唾液腺を刺激する力が弱くなる)、そして、口の乾燥のかげに、糖尿病や腎臓病、自己免疫疾患「シェーグレン症候群」などの病気が隠れていることもあります。
唾液の役割は?
ー唾液にはどのような役割があるのでしょうか?
寺内 一つは、自浄作用・殺菌作用です。口のなかは、唾液で潤うことによって、自浄作用・殺菌作用が働き、細菌の繁殖を防いだり、外からの菌の侵入を防いだりしています。虫歯を防ぐ働きもあり、口のなかを酸性・アルカリ性のどちらかに傾かないようにする調整も行っています。また、食べ物を飲み込んだり、おしゃべりがスムーズにできたりするのも、唾液によって口のなかがなめらかになるからです。
ー唾液にはいろいろな働きがあるのですね。
寺内 はい。唾液が減って口のなかが乾燥すると、口のなかの自浄作用・殺菌作用が低下し、細菌が繁殖しやすくなります。すると、口臭や虫歯、歯周病が起こりやすくなり、感染症にもかかりやすくなります。唾液の減少によって食べ物を飲み込みにくくなったり、おしゃべりをしにくくなったりすることは、生活の質の低下にもつながります。
ー唾液が出にくくなることで、口のなかや歯の健康が損なわれやすくなるのですね。
唾液の減少に女性ホルモンは影響している?
ー唾液の分泌量の低下に、女性ホルモンの低下は、影響しているのでしょうか?
寺内 唾液の分泌量の低下と女性ホルモンとの間に関連があることを示す確かな根拠はまだなく、よく分かっていないのが現状です。
けれども、更年期以降、口の乾燥を訴える方が増えること、それは男性よりも女性に多いこと、そして、女性ホルモンの受容体が、唾液腺や口腔粘膜に分布していることは分かっていますので、関係がある可能性はあると思います。
ドライマウスのセルフケアは?
ードライマウスのセルフケアにはどのようなものがありますか?
寺内 広く知られているものに唾液腺マッサージがあります。耳や顎の周りには、耳下腺、顎下腺、舌下腺といった唾液を分泌する腺があります。その唾液腺を指の腹で優しくマッサージすると唾液がでてきます。

ほかに、よく噛んだり、口を動かしたりすると、それが刺激となって唾液が分泌されやすくなります。口を「う」の形にすぼめた後に、「い」の形にして横に広げる口の体操など、表情を大きく動かしたり、人と会話したりすることも唾液の分泌を促します。
また、ドライマウスのケア用品に人口唾液がありますが、そうしたものを使ってみるのも一つです。食塩水のような感じのもので、スプレータイプや粘度のあるジェルタイプなどがあり、薬局で購入できます。
ストレスが口の乾燥につながることがあります
寺内 今お話ししたドライマウスは唾液が減ることで起こりますが、そうした症状を訴えられる方がいる一方で、唾液の減少は見られないけれど、「口が乾くんです。そして、舌がピリピリ痛むんです」と訴える方もいらっしゃいます。
ーなぜ、唾液が減っていないのに、口の乾燥を感じるのでしょうか?
寺内 心理的なストレスが関係していると考えられます。実は、口の乾燥は、代表的な心身症(心理的なストレスが身体的な症状として現れること)の一つなのです。
例えば、口内炎などもなく、唾液の分泌量も減っていないけれど、舌の痛みが続くような場合、患者さんのお話をよく聴いていますと、患者さんが大きなストレスを抱えていることが分かることがあります。
このように、原因はよく分からないけれど、舌がピリピリしたりヒリヒリしたりする痛みのことを舌痛症(ぜっつうしょう)といいます。
ーストレスによって、舌が痛くなることがあるのですね。知りませんでした。
寺内 ほかに、味覚障害を訴えられる方もいます。新型コロナウイルス感染症の症状に味覚障害がありますが、パンデミック以前から、更年期外来で味覚障害を訴えられる方は一定数いらっしゃいました。
ー舌痛症や味覚障害の治療には、どのようなものがありますか?
寺内 口が乾燥する感じがして、舌も痛むけれど、これといった原因がなく、精神的な背景があると考えられる場合は、患者さんによって異なりますが、不安や心配を和らげる抗うつ薬や漢方薬を処方する場合もありますし、認知行動療法を行う場合もあります。
栄養面では、ミネラルの不足が影響していることが考えられますので、鉄や亜鉛の値を計測して、栄養面の問題がないかを確認し、食事指導を行うこともあります。
ー更年期は女性を取り巻く環境が変化しやすく、大きなストレスも重なりやすい時期です。口が乾燥して生活に支障が出ているときは、自己判断せずに、医師の診察を受けることが大切ですね。
女性ホルモンの歯周病への影響とは!?
ー歯周病についても教えていただけますか?
寺内 歯周病は、歯を支える歯肉(歯ぐき)と歯槽骨(骨)が壊れていく病気です。歯の磨き残しなどによって、歯と歯ぐきの境目(歯周ポケット)に歯石(細菌)がたまり、炎症が起こることで引き起こされます。初期には自覚症状がありませんが、進行すると歯を支えている骨が溶け、歯が抜け落ちてしまいます。
ー女性ホルモンの影響はありますか?
寺内 あります。ありますが、女性ホルモンが豊富に分泌されている妊婦さんが歯周病になりやすいのです。妊婦さんの約8割が歯周病になるという報告もあります。妊婦さんが歯周病になると早産のリスクが高くなりますので、注意を払う必要があります。
ーこれまで、女性ホルモンが減ることで、更年期の不調が現れやすくなるというお話を伺うことが多かったのですが、歯周病については逆なのですね。
寺内 はい。女性ホルモンが歯周病の原因となる病原菌を増加させることが分かっています。女性ホルモンは女性の健康を守る良いものというイメージがあると思いますが、こと歯周病に関しては違うということです。
一方で、加齢や唾液の減少などの影響で、歯周病になる人は年齢を重ねるほど増えていきます。歯周病は口のなかのことだけに留まらず、全身に影響を及ぼしますので、年代を問わず、歯周病ケアをしっかり行うことが大切です。
歯周病は全身性の炎症を引き起こします
ー歯周病が全身に影響するのですか?
寺内 はい。歯周病は全身性の炎症を引き起こします。歯周病菌によって歯の周囲で炎症が起こると、毒性のある炎症性物質が歯ぐきの血管に入り込み、血液にのって全身をめぐります。
歯周病によって早産のリスクが高くなるのは、歯周病菌による炎症が子宮周囲の筋肉の炎症に波及するからです。妊娠初期に妊婦さんの口腔内衛生を指導するのには、こうした理由があるのです。
ー歯周病による全身への影響は、ほかにどのようなものがありますか?
寺内 歯周病菌は、動脈硬化を引き起こしたり、糖尿病を悪化させたりします。骨粗鬆(しょう)症や慢性関節痛リウマチ、認知症との関連も指摘されているところです。
ですので、毎日の歯磨きをしっかり行い、フロスなども使用して歯間もきれいにし、定期的に歯科検診を受けて、歯周病にならないように心がけることが大切です。
口腔内環境については、更年期外来や産婦人科で診察を行う際の視点から、ごく基本的なことをお話ししました。歯や口のなかのことについてより詳しく知りたい方は、日本歯科医師会のWEBサイト内にある「テーマパーク8020(ハチマルニイマル)」を参考にされるとよいと思います。一般の方向けに分かりやすく解説されています。
ー唾液が健康のために重要な働きをしていることや、口のなかのことが全身に影響することがよく分かりました。口臭や虫歯、歯周病を防ぐためにも、毎日の歯磨きをしっかり続けていきたいと思います。今回も貴重なお話をありがとうございました。
<この記事を監修いただいた先生>

寺内 公一 先生
東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 茨城県地域産科婦人科学講座 教授
▼詳しいプロフィールを見る
<インタビュアー>

満留 礼子
ライター、編集者。暮らしをテーマにした書籍、雑誌記事、広告の制作に携わる傍ら、更年期のヘルスケアについて医療・患者の間に立って考えるメノポーズカウンセラー(「NPO法人 更年期と加齢のヘルスケア」認定)の資格を取得。更年期に関する記事制作も多い。