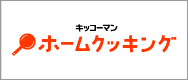エクオールとゲニステインの違いとは?女性の健康を支える大豆由来成分を徹底比較
イライラやホットフラッシュ、動悸といった更年期の不調を緩和する成分に、エクオールとゲニステインがあります。エクオールとゲニステインは、どちらも大豆イソフラボン由来の成分で、女性ホルモンであるエストロゲンと構造が似ているため、更年期のゆらぎをサポートすると考えられています。
しかし、このエクオールとゲニステインには、構造や体内での働きに違いがあることをご存知でしょうか。この記事では、エクオールとゲニステインの違いを詳しく比較します。どちらかを選ぶ前に、ぜひ参考にしてください。
エクオールとは?
大豆イソフラボンは、糖が付いていて体に吸収されにくい「グリコシド型」と、糖が外されていて吸収されやすい「アグリコン型」に分けられます。さらにアグリコン型は、「ダイゼイン」「ゲニステイン」「グリシテイン」に分類されます。
エクオールとは、大豆イソフラボンアグリコンの一つであるダイゼインから変換されてできる成分です。
大豆イソフラボンが腸内で代謝されて生まれる成分
エクオールにはエストロゲン様作用があり、更年期症状の緩和に効果があるとされますが、大豆食品を摂ればすぐに体内で吸収される成分というわけではありません。
大豆イソフラボンのうち、ダイゼインが消化管に到達し、腸内細菌によってエクオールに変換されることで、腸管から吸収できます。
ただし、エクオールを産生できる腸内細菌を持っている日本人は約2人に1人。つまり、エクオールは誰にでも作れるわけではないのです。
ちなみに、欧米諸国では10人に2~3人まで減ります。欧米と比べれば、日本人は多いほうですが、それでも作れる人は限られています。
エストロゲン様作用があり、更年期対策に注目されている
エクオールには、ホットフラッシュや首・肩の凝りの改善、目尻のシワの軽減、骨密度の減少抑制、血管機能の改善といった更年期症状の緩和効果が報告されています。
また、エストロゲンの働きを整える点も、エクオールの特徴です。エストロゲンが過剰に分泌されたとき、エクオールがエストロゲンの受け皿であるエストロゲン受容体に先に結びつくことで、エストロゲンの強すぎる影響を抑えてくれます。こうした調整力があることから、より自然に体をサポートしてくれる成分として注目されています。
さらに、エクオールには抗アンドロゲン作用もあります。これは、前立腺がんや毛髪の脱毛の原因である、アンドロゲン(男性ホルモン)の過剰な働きを抑えるものです。
ゲニステインとは?
ゲニステインとは、腸内細菌の有無に関係なく体に取り入れられるアグリコン型イソフラボンの一つです。ゲニステインはアグリコン型イソフラボンのなかで、女性ホルモン様作用が最も強いことが分かっています。
大豆イソフラボンの主要な成分の一つ
ゲニステインは、アグリコン型イソフラボンのなかで、最もエストロゲン様作用が強い成分です。構造がエストロゲンによく似ているため、体内のエストロゲン受容体に直接結合し、女性ホルモンに似た作用を示します。これにより、不眠やめまい、頭痛、イライラ、疲労感といった更年期症状の緩和に役立ちます。
またゲニステインは、エクオールのように腸内細菌による変換を必要とせず、誰でも、摂取すれば効果が期待できるというメリットがあります。
抗酸化作用や抗炎症作用もあり、幅広い効果が期待される
ゲニステインは、更年期症状の緩和だけでなく、骨粗しょう症の予防や乳がんリスクの低下、動脈硬化の予防など、幅広い効果が期待されています。
●乳がんのリスクの低下
エストロゲンは、乳がんの発症や進行に深く関わるとされています。ゲニステインは、エストロゲンの代わりに、乳がん細胞の受容体に先に結合することで、エストロゲンの働きを妨げ、がん細胞の増殖を抑制すると考えられています。
●骨粗しょう症の予防
エストロゲンには、骨のなかにカルシウムを蓄える働きがあります。そのため、エストロゲンの分泌が減ることで、骨粗しょう症のリスクが高くなります。そこで、ゲニステインを摂取することで、エストロゲンのように骨量の減少を抑えることが期待できます。
●抗酸化作用
更年期世代の女性は、加齢とともに抗酸化力が低下します。この変化により、体内の活性酸素が増え、細胞がダメージを受けやすくなり、がんや動脈硬化などのリスクが高まります。こうした影響をやわらげるのが、大豆イソフラボンが持つ抗酸化力です。日常的に摂取すると、病気の予防だけでなく、肌の調子を整えるといった美容面でも良い効果が期待できます。
●動脈硬化の予防
更年期以降は、女性ホルモンの減少により、LDLコレステロール値が上昇しやすくなります。これが動脈硬化の原因となるケースも少なくありません。大豆イソフラボンには、LDLコレステロールや中性脂肪を減少させる作用があることが分かっており、動脈硬化を含む生活習慣病の予防にも役立ちます。
●血糖値調整
血糖値を下げ、インスリン感受性を改善する効果が、ゲニステインにはあると報告されています。また、このインスリン感受性の改善により、糖尿病の予防にもつながることが期待されています。
●認知機能の維持
ゲニステインには、認知機能を改善する効果も報告されています。アルツハイマー病の初期症状がある患者がゲニステインを摂取することで、病気の進行が遅くなる可能性が示されています。
エクオールとゲニステインの違いとは?
エクオールとゲニステインは、どちらも更年期症状の緩和や健康に良い効果がある成分です。エクオールとゲニステインの違いを理解して摂取すれば、より自分に合ったサポートが期待できます。
構造と体内での生成経路の違い
エクオールは、ダイゼインが腸内細菌で変換されてはじめて生成される成分です。エクオールを変換できる腸内細菌は、日本人の2人に1人しか持っておらず、体内でエクオールを作れる人と作れない人がいます。
それに対してゲニステインは、腸内での変換が不要で、摂取すればそのまま吸収されるので、体質にかかわらず効果が期待できます。
産生者/非産生者によって効果が変わるエクオール
エクオールを産生できるかどうかは、自分自身では判別できず、簡単な尿検査が必要です。エクオールの摂取を検討されている方は、まず検査してみましょう。
エストロゲン様作用と結合力の強さと安定性の違い
エクオールとゲニステインは、どちらもエストロゲン様作用があり、更年期症状を緩和する働きがあるとされています。しかし、エストロゲンに近い構造を持っているゲニステインのほうが、エストロゲン様作用は強いといわれています。
キッコーマンがゲニステインに着目し始めたきっかけ
1990年代、消費者の健康ニースが高まり始めた頃に醤油原料である「大豆の機能性成分」に焦点をあてて、研究を開始しました。
当時、イソフラボン自体が女性の健康に寄与することは既に知られていましたが、アグリコン化され体内に吸収されることを突き止めたのはキッコーマンの研究成果です。
醤油を絞った後の固形部分に含まれているイソフラボンが、醸造の工程で麹菌など発酵の影響を受けアグリコン化していることを見つけ、アグリコン化した成分の吸収性が高いことは他成分において知られていたため、大豆イソフラボンアグリコンも同様の効果があるのでは、と仮説を立てたのです。
研究の結果、大豆イソフラボンアグリコンの吸収性が高いことが分かり、また、そのなかでもエストロゲン活性が最も高いゲニステインと健康寄与について、日々研究を重ねています。

まとめ|自分の体質に合った選択を
どちらも大豆由来の有用成分。体質に合うものを毎日摂取することが大切
エクオールとゲニステインはどちらも注目の成分ですが、ゲニステインのほうがエストロゲン様作用は強く、エクオール検査も不要です。一方、エクオールは、日本人の半数しか持っていないという腸内細菌が必要になります。
また、エクオールやゲニステインを食事から摂取しようとすると、味噌、醤油、豆腐、納豆など、さまざまな大豆製品を日常的に取り入れる必要があります。しかし現実的には、忙しい毎日に十分な量の大豆製品を食べ続けるのは難しいもの。特に、味噌や醤油などの調味料は、摂り過ぎると塩分過多になる可能性も。
こうした課題を補うには、ゲニステインを含むサプリメントの活用も一つの方法です。必要な成分を確実に摂取でき、エクオール検査を受ける必要もありません。バランスの取れた食事に併せて、ゲニステインを含むサプリメントを上手に活用して、更年期症状の改善につなげてみてはいかがでしょうか。
<この記事を監修いただいた先生>
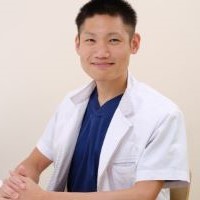
秋津 憲佑 先生
キッコーマン総合病院 産婦人科部長
▼詳しいプロフィールを見る