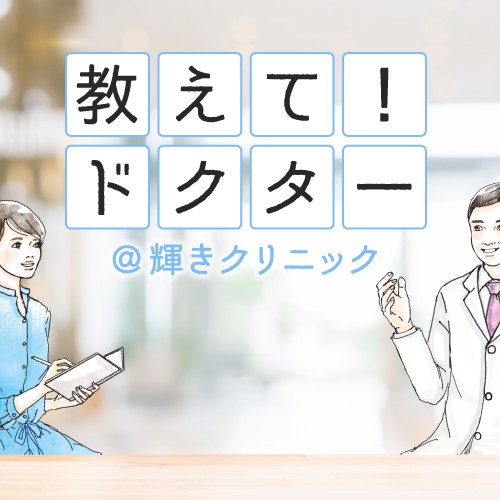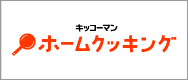更年期の疲労感・倦怠感について
更新日: 公開日:
学ぶ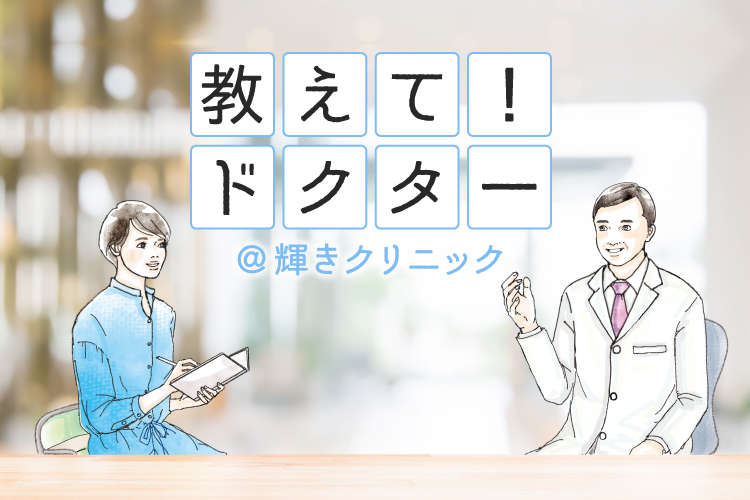
更年期を迎えて、疲れやすさを感じる人は多いようです。疲労感や倦怠感、体のだるさは、更年期以外でも感じることがある症状の一つです。そのため、このままやり過ごしてよいのか、それとも病院で診察を受けるほうがいいのか迷う人もいるのではないでしょうか。そこで今回は、更年期の専門医である東京科学大学の寺内公一先生に、更年期と疲労感についてお話を伺いました。
疲労感は更年期に現れやすい症状の一つ
―更年期になって疲れやすくなったという声をよく聴きます。
寺内先生(以下、寺内) 疲れやすさや疲労感は、更年期の特徴的な症状の一つといえます。当院の更年期外来を受診されている患者さんを対象に、疲れやすさの頻度について調べたところ※1、「ほぼ毎日」疲れを感じている方は49.3%、「週3~4回」は15.1%、「週1~2回」は21.2%で、合計すると、「週1回以上疲れやすさ」を感じる方は85.6%もいらっしゃることが分かりました。
また、地域住民で更年期の方・約850名を対象にした調査※2でも同様の結果となり、約85%の方が疲れやすさを感じていることが示されています。
その調査では、ほかの更年期症状の有無も調べていますが、20ほどある更年期症状のなかで最も多かった症状は、疲れやすさでした。
また、この調査では同様の内容を、オーストラリアの地域住民(更年期の方・約890名)にも行っているのですが※2、日本の調査と同様に、約82%と多くの方が疲れやすさを感じており、更年期症状のなかで最も訴えの多い症状も疲れやすさでした。
―オーストラリアでも日本と同様の結果になったのですね。疲れやすさは、更年期以外でも感じることがある症状の一つですが、更年期以外では、どれくらいの方が疲れやすさを感じているのでしょうか。
寺内 病院にかかっていない一般の方を対象にした調査では、6.7%の方が慢性的に疲労を感じている※3という報告があります。また、かかりつけ医を受診している方を対象にした調査では、13.6%の方が疲労を訴えている※4ことが分かりました。
―更年期に疲れやすさを訴えられる方が8割ほどいるのに対して、更年期以外では1割ほどと、大きな差がありますね。更年期は疲れやすいのですね。
※1 Terauchi 2014 Evid-Based Compl Alt 2014:593560
※2 Anderson 2004 Climacteric
※3 Walker 1993 J Gen Intern Med
※4 Cathebras 1992 J Gen Intern Med

疲労感と関連する要素は?
寺内 私たちが最近行った研究では、更年期女性の疲労感には、女性ホルモンのゆらぎ、不眠、うつ症状、握力の低下の4つが関連することが分かりました。
―女性ホルモンのゆらぎについて簡単に説明をお願いします。
寺内 更年期は、卵巣機能の低下にともない、女性ホルモンの分泌量が急激に少なくなっていきます。けれどもそれは、坂道のように一直線に減っていくのではなく、波打つように大きくゆらぎながら、あるときは多く分泌したり、またあるときは少なかったりしながら減っていきます。
女性ホルモンがゆらぐ時期は、うつ症状や不眠のリスクが高くなることが知られています※5。ゆらぎの時期は、血管運動神経症状(ほてり・のぼせ・ホットフラッシュや発汗など)が起こりやすく、就寝中にホットフラッシュが起きると、睡眠の質が落ち、それが主観的な不眠(眠れないと感じること)につながると考えられています。不眠が疲労感と関連している※6ことは、理解しやすいと思います。
また、更年期女性を取り巻く環境は、大きく変化しやすいことがあります。不安や心配事があれば、眠りの質も落ちてしまいますし、過度なストレスがうつ症状につながることもあります。
―握力が疲労感に関連するのですね。意外でした。
寺内 はい。握力が低い方のほうが、疲労感が強い傾向があります。ただしこれは、私たちの研究だけでなく、サルコペニア(筋力などの低下)※7の判定にも握力は用いられていますし、ほかの研究においても、筋力低下は慢性疲労症候群と関連し、握力テストは、全身の筋肉の疲労度を評価するための指標であることが示されています※8。
私たちは、うつ症状や不眠が重度の疲労につながり、それが筋力の低下として現れているのではないかと推測しています。私たちの外来では筋力評価のために常に握力を測定しているのですが、“握力が弱いときは、疲労感が強いのかもしれない”と考える、一つの目安にしています。
※5 Terauchi 2010 Climacteric, Terauchi 2012 Maturitas, etc.
※6 Hirose, Terauchi 2016 Climacteric
※7 加齢によって骨格筋の量が低下し、筋力や身体機能が低下した状態
※8 Jakel 2021 J Transl Med
ゆらぎの時期はどれくらい続く?
―更年期のゆらぎによる不調は、どれくらいの期間続くのでしょうか?
寺内 一概には言えませんが、更年期の不調のコアタイム(激しいゆらぎの時期)は、閉経の前後2年、合わせて4年ほどといわれています。うつ症状については、閉経後2年経つと、うつ症状を起こすリスクが半減するというデータ※9もあります。
私の実感としても、更年期外来で、疲労感やほかの更年期症状を訴えていた方が、閉経してゆらぎが治まると、「疲れにくくなった」「症状が落ち着いた」とお話されることが多いように思います。
―そうなのですね。更年期の不調のコアタイムがどれくらいなのか、その目安がわかると、つらい時期がずっと続くわけではないと、気持ちが少し明るくなりますね。
※9 Freeman 2014 JAMA Psychiatry
疲労感の背景にあるものは?
寺内 更年期外来で疲れやすさを訴えられる方は多いのですが、その背景にあるものは、患者さんお一人おひとり異なるとも感じます。
以前、更年期と睡眠の関係についてお話をしたときに、BPSSモデル(バイオ・サイコ・ソシオ・スピリチュアルモデル)についてお話をしました。
更年期症状は、「身体的(bio)」「精神的・心理的状態(psycho)」「社会的(social)」の3つ、または「信念・生き方(spiritual)」を加えた4つの側面から考えることが大切です、という視点です。
患者さんのお話に、日々、耳を傾けていますと、疲れやすさの原因は一つではなく、女性ホルモンのゆらぎに加えて、加齢の影響、不安・うつ症状の強さ、生活習慣、どのように生きたいか、といったことが、重なって現れていると感じます。
加齢については、どなたも年齢を重ねます。20歳のときと、50歳のときでは、体力的に違いがあるのは、ごく自然なことです。
更年期は家庭のこと、仕事のこと、家計のこと、子どもの進学や就職、家族や自分自身の病気、身近な人の死、介護など、すぐに解決できないような問題をいくつも同時に抱えやすい時期です。そのため、不安が強くなるのも、無理からぬことと思います。
そして、生活習慣の乱れが疲れやすさを悪化させていくこともあります。患者さんのお話をよく聴いていますと、例えば、忙し過ぎて食事の栄養バランスが偏っていたり、献身的に介護をされていて睡眠時間が短くなっていたなど、体力的に厳しい状況だったりした、ということが分かることもあります。
こうしたことは、ご本人は自覚されていらっしゃらないことが多いのですが、診察で患者さんご自身のお話をよく聴いていくなかで、患者さんご自身が、生活習慣の偏りやがんばりすぎていることに気づいていかれることはよくあります。
―更年期の女性は周囲から必要とされて多忙ですから、気づかないうちに生活習慣が乱れて、疲れやすくなっていることがあるのですね。
更年期症状の疲労感と似ている病気
―更年期の疲れやすさと間違えやすい病気について教えてください。
寺内 様々なことが考えられますが、そのなかでも、更年期症状とよく似ているといわれるのが、甲状腺機能低下症です。甲状腺は、のどぼとけにある臓器で、全身のエネルギーの使い方をコントロールするホルモンを作っています。 けれども、その機能が低下して、甲状腺ホルモンの分泌ができなくなると、エネルギーを使ったり、新陳代謝を促したりする機能が落ちてきます。そうすると、疲労感や冷え、むくみ、眠気、無気力、記憶力低下などの症状が現れやすくなります。
治療法について
―疲労感がある場合、このままやり過ごしてよいのか、それとも病院で診察を受けるほうがよいのか迷うことがあると思います。
寺内 このあとセルフケアのお話をしますが、セルフケアを行ってみても、疲労感や気分の落ち込み、不眠が続くなど、日常生活に支障が出ている場合は、今感じている疲労感が更年期によるものかを見極めるためにも、早めに更年期に理解の深い医師の診察を受けてほしいと思います。採血などの検査を通じて、疲れやすさの背景にあるものを、ある程度絞り込むことができます。
疲労感の陰に、先ほどお話しした甲状腺機能低下症、うつ病、不眠症がかくれている場合もありますし、ほかにも、疲れやすいと思っていたら、心臓や肝臓の病気が見つかったという例もあります。疲労感が病気によるものの場合は、適切な治療法や薬によって治療することが必要です。
注意が必要なのは、「眠ったはずなのに起きたら疲れている」といった不眠の場合です。「閉塞性無呼吸症候群」は、一般的には肥満型の男性の病気と捉えられがちですが、更年期以降は女性にも増加する病気で、痩せている方でもかかります。閉塞性無呼吸症候群については、「更年期の不眠は心の状態も気にかけることが大切」でお話ししています。
また、疲労感には、なんとなく疲れが抜けないといった“漠然とした疲労感”もあります。そうした症状には、漢方医学のアプローチが有効な場合があります。
漢方医学では、疲労感は体のなかのエネルギーを作り出す力が弱くなっている状態と考えますので、気力や体力、エネルギーを増やすように働く補剤を中心に処方します。代表的なものに、補中益気湯(ほちゅうえっきとう)、十全大補湯(じゅうぜんたいほうとう)、人参養栄湯(にんじんようえいとう)があります。

おすすめのセルフケアは?
―家庭で手軽に取り組めるセルフケアがあれば、教えてください。
寺内 質の良い睡眠、栄養バランスの良い食事、適度な運動を心がけることだと思います。
睡眠については、質の良い睡眠がとりたくても、とれない方もいらっしゃると思います。それが就寝時刻や寝室の環境など、調整しやすいものであれば調整し、周囲にもサポートを求めていくとよいのではないでしょうか。
―夜間にホットフラッシュが起きて、汗をかいてしまう人のなかには、着替えを枕元に置いて、着替えやすくしたり、寝室を自分に合う室温や湿度に調節したりする人もいるようです。「輝きプロジェクト」で紹介されているセルフケアも参考になりますね。
寺内 食事については、栄養バランスの良い食事をベースに、その補完として、ビタミンB1を含む食材を食べるとよいのではないでしょうか。ビタミンB1は、鈴木梅太郎氏が、米ぬかに含まれる物質として発見した成分です。ビタミンB1が不足すると、脚気になることが知られています。初期症状は、全身のだるさや疲れやすさで、手足のしびれや下肢のむくみなども現れます。
―脚気は、昔の病気のではないのですか。
寺内 食料事情が改善した現在でも、栄養価の非常に低い食品ばかりを食べ続けている人や、アルコール依存症の人にみられます。
―そうなのですね。知りませんでした。
寺内 ビタミンB1を多く含む食材には、豚肉やグリンピース、大豆などがあります。また、にんにくにはアリシンという臭気成分が含まれていますが、ビタミンB1と結合して、アリチアミンという成分に変換されると、体内への吸収が良くなります。
併せて、女性ホルモンと似た働きが期待できる、大豆イソフラボンを含む大豆製品や、骨粗しょう症対策に、カルシウムを含む乳製品や小魚なども、意識して食べるとよいのではないでしょうか。
―食事の補完として、サプリメントも上手に利用したいですね。適度な運動に関してはいかがでしょうか。
寺内 適度な運動は、肥満予防になるだけでなく、心身に良い影響を与え、更年期の不調を和らげることは、よく知られています。ふだんの運動習慣の差は、体力に影響しますので、生活習慣において、運動不足だと感じる場合は(その方が運動できる状況にあれば)、運動を取り入れるのも良いと思います。
また、朝、太陽の光を浴びると、体内時計がリセットされ、夜、眠りにつきやすくなります。ウオーキングやストレッチなどは、日々の暮らしに取り入れやすいのではないでしょうか。
―更年期に疲労感を感じている方が多いこと、そして疲労回復には、質の良い睡眠、栄養バランスの良い食事、適度な運動が大切なことがよく分かりました。生活習慣を見直すことも大事ですね。今回も、貴重なお話をありがとうございました。
<この記事を監修いただいた先生>

寺内 公一 先生
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科茨城県地域産科婦人科学講座教授
▼詳しいプロフィールを見る
<インタビュアー>

満留 礼子
ライター、編集者。暮らしをテーマにした書籍、雑誌記事、広告の制作に携わる傍ら、更年期のヘルスケアについて医療・患者の間に立って考えるメノポーズカウンセラー(「NPO法人 更年期と加齢のヘルスケア」認定)の資格を取得。更年期に関する記事制作も多い。