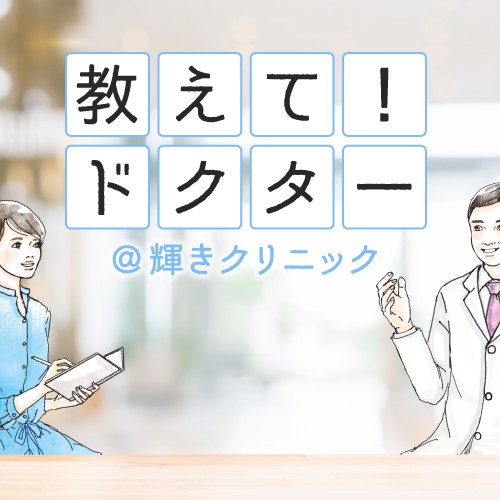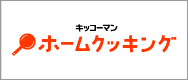専門医に聞く、ホットフラッシュの原因と症状および対策
更新日: 公開日:
学ぶ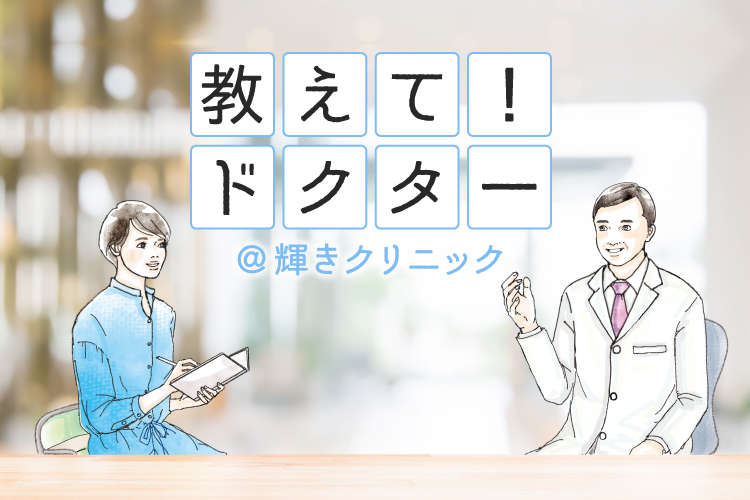
更年期に多くの人が経験するホットフラッシュ。最新の研究や調査によって、ホットフラッシュが引き起こされるメカニズムが解明され始め、症状を和らげる新薬の登場も期待されています。そこで今回は、更年期の専門家である東京科学大学の寺内公一先生に、ホットフラッシュについてお話を伺いました。更年期を上手に乗り切るヒントがいっぱいです!
ホットフラッシュの治療法。薬、心理療法、セルフケアの注意点
<ホットフラッシュのセルフケアは、自分に合うものを選んで>
―滝のように汗が出て止まらなくなったり、顔が急に熱くなったり、のぼせて顔が赤くなったりする血管運動神経症状(VMS)は、更年期症状のなかでも経験することの多い症状です。予防の観点からセルフケアについてお伺いしたいのですが、血管運動神経症状のホットフラッシュ(ほてり・のぼせ)、発汗の予防に役立つ栄養素や食べ物はありますか?
寺内公一先生(以下、寺内) 当院の更年期外来で、血管運動神経症状と摂取栄養素との関係を調べたところ、ビタミンB6を摂っている人ほど、血管運動神経症状の発症頻度が少ないことが分かりました。ビタミンB6は、にんにくや肉、魚の赤身などに多く含まれています。「普段からビタミンB6を摂っている人は、血管運動神経症状の発症頻度が少ない」というデータは、私たちの研究※1以外にもいくつかあります。
―栄養バランスの良い食事を心がけながら、ビタミンB6を多く含む食材を意識して食べたり、日々の食事の補完としてビタミンB群をまとめて摂れるサプリメントを利用したりするのも一つですね。

寺内 ビタミンB6以外では、血管運動神経症状と大豆イソフラボンの関係を調べた研究も多くあります。大豆イソフラボン は、女性ホルモンのエストロゲンと化学構造式が似ていて、体内でエストロゲンに似た働きをすることが知られています。
―大豆イソフラボンを分解して、体内に吸収されやすい形にした「大豆イソフラボンアグリコン」のサプリメントも人気ですね。食事以外のセルフケアには、どのようなものがありますか?
寺内 仕事や家庭でさまざまな疲れやストレスが、蓄積している方も多いと思いますので、少しの時間でも休息や気分転換、リラックスできる時間をつくり、心身のバランスを整えることも大切だと思います。
というのは、更年期症状以外に特に大きなストレスがない方は、ホットフラッシュや発汗の症状があっても、自分でなんとかやり過ごしている方が多いように思います。その一方で、さまざまな問題を抱えて、大きなストレスを抱えている方は、コップの水があふれそうな状況ですから、そこにホットフラッシュや発汗の症状が加わることで、もう対処できない…となる方が多いように思います。
―更年期に、運動や入浴法、アロマテラピー、ツボ指圧、鍼療法、自律訓練法などを実践している人は多いと思いますが、どれもリラックスを促すものですね。
寺内 セルフケアは治療や薬とは異なりますので、医学的に効果が証明されているものばかりではありませんが、ゆらぎがちな心身の調子を整えることに役立ちます。体調管理の一つとして、自分に合うものを選んで継続して取り組めると良いのではないでしょうか。

<ホルモン補充療法(HRT)、漢方薬、向精神薬など、治療法の選択肢も多い>
―血管運動神経症状の薬には、どのようなものがありますか?
寺内 患者さんのお話をよくお聴きして、生活習慣の改善をご提案しながら、必要な場合は、薬物治療を行います。ホットフラッシュや発汗の症状に対する薬物療法には、ホルモン補充療法(HRT)、漢方薬などがあります。
ホルモン補充療法は、血管運動神経症状の発症頻度を少なくするという研究データが豊富にありますし、漢方薬の加味逍遙散(かみしょうようさん)、桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)は、効果があるとされています。
―乳がんの既往歴がある方は、ホルモン補充療法を受けられますか?
寺内 乳がんの既往歴がある方は、ホルモン補充療法を行うことができません。
また、女性ホルモンのエストロゲンでがん細胞が増殖するタイプの患者さんは、乳がんの治療として、エストロゲンの働きを抑えるホルモン療法を行うと、血管運動神経症状が現れやすくなることが知られています。また、漢方薬を続けてみたけれど、症状が良くならない場合もあります。
そんなとき、選択肢の一つとして、ホルモン補充療法でも、漢方薬でもない薬を使うことがあります。
例えば、過活動膀胱の薬です。過活動膀胱は、すぐトイレに行きたくなってしまう病気で、治療として自律神経の働きを整える薬を使います。
発汗も自律神経(副交感神経)の働きによるものですから、過活動膀胱の薬で血管運動神経症状(特に発汗)の発症頻度が少なくなることが、データとして示されています※2。
また、血管運動神経症状がある人は、不眠やうつ・不安を経験しやすいため、不眠を訴える方には睡眠薬を、うつ・不安がつらい方には向精神薬(抗うつ薬、抗不安薬、催眠鎮静薬)を処方することもあります。
抗うつ薬のSSRIは、うつ症状のない方にも血管運動神経症状に対する効果があることが報告されています※3。
―血管運動神経症状には、いろいろなアプローチがあるのですね。
<自分の体に何が起きているのかを知る「知識の備え」も有効です>
―ホットフラッシュや発汗は、いつ起こるか自分ではよく分かりません。どのような心構えでいるとよいでしょうか?
寺内 自分の体に起きていることを俯瞰するといいますか、一歩引いて考えてみるといいと思います。それを行いやすくするのが、認知行動療法です。血管運動神経症状のホットフラッシュや発汗への治療効果も証明されています。
―認知行動療法とは、どのようなものですか?
寺内 ごく簡単な説明になりますが、今の状況を“正しく”理解して、認知のゆがみや考え方のクセに気づき、自分の行動を修正することによって症状を改善していく心理療法です。
―なぜ、認知行動療法を行うと症状が改善するのでしょう?
寺内 私の見解になりますが、客観的に自分の置かれた状況を把握したり、理解したりすることは、どんな局面でも大事なことだと思います。ホットフラッシュや発汗が起きたときに、自分の状況を俯瞰して、一歩引いて把握できると冷静になれますので、それが症状緩和に結びつくのではないかと思います。
言い換えれば、症状が現れたときに、自分の体に何が起きているのかよく分からない…という状況は、あまりよくないと思います。症状そのものに加えて、不安を感じたり動揺しやすくなったりすると思いますので、より強く症状を感じやすくなるのではないでしょうか。
例えば、滝のように汗が出て止まらなくなったときに、「これは更年期症状で、それで汗をかいて熱を逃がしているのかもしれない。しばらくすれば治まるだろう」と冷静に考えられると、症状をコントロールしやすくなると思います。
―そうですね。今、体で何が起きているのかを知っておくことも大切ですね。ところで、夏の暑い時季にホットフラッシュや発汗が起きやすいように思うのですが、何か関連はあるのでしょうか。
寺内 暑いからというよりも、夏は室外がとても暑く、室内は冷房で冷えていて、環境温度が激変します。そのことが、影響していると考えられます。
その意味では冬も同様で、寒いからホットフラッシュや発汗が起こりにくいかというとそうではありません。寒い屋外から暖房のよく効いた暖かい部屋に移動したときに起こることは珍しくありません。
―環境の変化によって、ホットフラッシュや発汗が起こりやすくなることが分かれば、汗を拭くハンカチの準備だけでなく、心の準備もできますね。
※1 Odai, Terauchi et al. 2019 Climacteric
※2 Simon 2016 Menopause
※3 Freeman 2011 JAMA

ホットフラッシュと不眠には深い関係が?
<更年期以降も血管運動神経症状が続く人はおよそ2割。80代以上の人も>
―血管運動神経症状は、更年期症状の一つで、日常生活に支障が出ることもありますね。
寺内 血管運動神経症状には、ホットフラッシュ(ほてり、のぼせ)、発汗などの症状があり、個人差もあります。発汗をともなうホットフラッシュを訴えられる方もいますし、ほてりだけ、大量の汗だけを訴えられる方もいらっしゃいます。特に大量の汗は、甲状腺機能亢進症や循環器疾患などによっても引き起こされることがありますし、手や脇など特定の部位だけに大量の汗をかく病気もありますので、更年期による発汗かどうか見極めることも大切です。
―更年期外来では、どれくらいの方が、ホットフラッシュや発汗を自覚されているのでしょうか?
寺内 当院の更年期外来で調べたところ、「顔があつくなる」をほぼ毎日自覚されている方は21.5%、週3~4回は15.1%、週1~2回は18.0%で、合わせると54.6%でした。「寝汗をかく」は、ほぼ毎日は16.8%、週3~4回は10.4%、週1~2回は17.4%で、合わせると44.6%でした。多い方ですと、1日に10回も20回もホットフラッシュが起きている方もいました。
―外来に通う2人に1人はホットフラッシュを自覚されているのですね。ところで、ホットフラッシュや発汗は更年期特有の症状だと思っていましたが、寺内先生が参加された研究の論文※4において、更年期以降もホットフラッシュや発汗を自覚している人がおよそ2割もいることが報告され、報道で取り上げられるなど注目を集めました。
寺内 ホットフラッシュや発汗を自覚されていても、必ずしも医療機関にかかるとは限りません。国立長寿医療研究センターとの共同研究※4では、医療機関を受診していない方も含めた地域住民女性を対象とし、どれくらいの方が血管運動神経症状を自覚しているのか、その割合を調べました。
―確かに、自分で折り合いをつけて、やり過ごしている方もいるはずですよね。
寺内 この調査※4では、ある地域で無作為に選んだ地域住民女性、約2300人のなかから、40~91歳の1152人を対象に、ホットフラッシュや発汗についてお聞きしました。
その結果、45~49歳は約26%、50~54歳は約45%、55~59歳は約32%の方が、ホットフラッシュや発汗を自覚していることが分かりました。特に50~54歳は、更年期のゆらぎの時期にあたる方々で、中等症の割合が一番多い年代という結果になりました。
さらに、この調査では、更年期以降もおよそ2割の方がホットフラッシュや発汗を自覚していることも分かりました。
―80歳以上でも、2割の方がホットフラッシュや発汗を自覚されていることに、とても驚きます。
寺内 当院の外来で、更年期以降もホットフラッシュや発汗で悩む方のお話をお聴きしていましたし、また大変困られていることも知っていましたので、今回の研究論文の結果は、私の臨床的な実感とも合致しています。
今の話と関連しますが、アメリカのSWAN研究※5においても、半数の方が閉経後に4年半以上も、ホットフラッシュや発汗を抱えていることが報告されています。
ホットフラッシュや発汗は、基本的には「ゆらぎ」による症状だと考えていますが、なかには「ゆらぎ」の時期が過ぎても症状が続いてしまう人もいるということです。

<ホットフラッシュがある人は不眠やうつ・不安を経験しやすい>
―国立長寿医療研究センターとの研究論文※4では、血管運動神経症状と不眠の関係についての報告も大変興味深いものでした。
寺内 ホットフラッシュや発汗の症状がある方と、症状のない方を比べた場合、入眠障害(寝つきが悪くなる)のリスクは、ホットフラッシュがある方のほうが約2倍高くなり、熟眠障害(ある程度眠ってもぐっすり眠れたという満足感が得られない)のリスクも2倍ほど高くなることが分かりました。
また、私が行った別の研究※6では、入眠障害には、「寝汗」と「不安」が関連し、熟眠障害については、「寝汗」と「うつ」が関連することが分かりました。
更年期に「よく眠れなくなる」ことは、以前から言われていましたが、その背景には、「ホットフラッシュ(ほてり・のぼせ)、発汗」「不眠」「うつ・不安」があり、それぞれがトライアングルのように結びつき、お互いに深く影響し合っているということだと思います。
―ホットフラッシュや寝汗だけでも大変なのに、不眠やうつ・不安も重なると、心身ともにつらくなりますし、それが長引けばなおさらですね。更年期の女性や、周囲の人にもぜひ知ってほしい情報です。
<つらい症状が続くときは抱え過ぎずに相談を>
―更年期以降のホットフラッシュや発汗に対しては、どのような治療法があるのでしょうか。
寺内 いわゆる更年期世代の方が、ホットフラッシュや発汗を訴えられる場合は、「更年期障害」として、比較的スムーズに治療方針を立てやすいのですが、例えば、70代、80代の方が、ホットフラッシュや発汗を訴えられた場合は、更年期は過ぎていますから、患者さんの訴えと治療法が、スムーズにつながらないことはあると思います。
それだけに、患者さんご自身もつらい思いを長く抱えていらっしゃるわけです。今のところ、日本にはホットフラッシュや発汗に特化した薬はありませんので、外来では、患者さんのお話をよくお聴きして、ホットフラッシュや発汗が起きている背景因子を見極めながら、ホルモン補充療法(HRT)、漢方薬など、症状の緩和が期待できる薬を用いた治療方針を立てていきます。
―更年期を過ぎても、ホットフラッシュや発汗がつらいときは、更年期外来を受診してよいでしょうか?
寺内 そうしてほしいと思います。婦人科医は、女性の体と心の専門家であり、更年期だけでなく、思春期、性成熟期、老年期と、生涯にわたって患者さんに寄り添い続けるパートナーです。ホットフラッシュや発汗に限らず、不調でつらいときは一人で抱えずに、早めに更年期に理解の深い婦人科を受診していただきたいと思います。
※4 Tomida, Otsuka, Terauchi, et al. 2021 J Obstet Gynecol Res
※5 Avis 2015 JAMA Intern Med
※6 Terauchi 2012 Maturitas 72:61

専門医に聞く、ホットフラッシュの原因と最新研究
<エストロゲンが減少すると、なぜ体温調節がうまくいかなくなるの?>
―体温調節は生きるうえで欠かせない機能ですが、それが更年期に誤作動を起こすのでしょうか?
寺内 誤作動を起こすというよりは、過敏になるということでしょうか。もともと体には、命に関わる脳や内臓を守るために、深部体温(体内部の温度)を一定に保つ仕組みが備わっています。例えば、深部体温が一定以上に高くなってきたら、汗をかいて熱を逃がすようにし、逆に深部体温が低くなってきたら、体を震わせて体温を上げようとします。
この深部体温が一定に保たれる範囲のことを、「サーモニュートラルゾーン」と呼んでいます。
ところが、更年期を迎えると、このサーモニュートラルゾーンが極端に狭くなり、わずかに深部体温が上がっただけでも温度調節のスイッチが入り、それほど暑くないのに、顔が赤くなったり、汗をどっとかいたり、ということが起こると考えられています。これが「サーモスタット仮説」※7です。
<ホットフラッシュのカギを握るのは「KNDyニューロン」>
―更年期になると、なぜサーモニュートラルゾーンが極端に狭くなるのでしょうか?
寺内 エストロゲンの分泌量が低下するとサーモニュートラルゾーンが狭くなることは、以前から分かっていたのですが、なぜそうなるのかまでは、よく分かっていませんでした。
ところが、2010年くらいから、どうやら脳の視床下部にある「KNDy(キャンディ)ニューロン※8」という神経とそれが分泌するホルモンが影響を与えているらしいということが分かり始めました。
―さきほど、更年期以降もホットフラッシュや発汗が長引く方がいるというお話でしたが、このことにもKNDyニューロンは関わっているのでしょうか。
寺内 それはまだよく分かっていません。けれども、これはあくまでも私の理解ですが、エストロゲンの分泌量が低下するとKNDyニューロンの活性が一時的に高まり、体温調節のスイッチが過敏になって、ホットフラッシュにつながります。けれども、一部の方には、その活性が固定されて更年期以降もずっと残ってしまい、そのためにホットフラッシュが長引いてしまうのではないかと考えています。
<ホットフラッシュに特化した新薬の研究・開発が進んでいます>
寺内 世界中でKNDyニューロンの研究が行われていますし、ホットフラッシュや発汗に特化した新薬の使用は、アメリカでは始まっています。
また、これは余談になりますが、ホットフラッシュについては、症状を抑える研究だけでなく、ホットフラッシュが、将来的に慢性疾患のバイオマーカーになりうるのではないか、という研究も進んでいます。
例えば、ホットフラッシュと動脈硬化の関連についてのアメリカの研究※9で、40~60歳の女性272人を対象に、ホットフラッシュの頻度を調べたところ、53歳以下のグループでは、「ホットフラッシュの頻度」と「血管内皮機能(血管を収縮・拡張したり、血栓の形成を予防したりする機能)」が負に相関することが分かりました。つまり、ホットフラッシュの頻度が高い人は、将来的に動脈硬化などの心血管疾患のリスクを抱えやすいのではないかという考え方です。
ホットフラッシュと認知症の関連を調べた研究もあります※10。45~67歳の女性272人を対象に、「ホットフラッシュの頻度」と「脳の画像」を記録したところ、ホットフラッシュの頻度が、大脳の白質病変(大脳白質が虚血状態になること)と相関することが分かりました。つまり、ホットフラッシュの頻度が多い人は、将来的に認知症のリスクが高いかもしれないという考え方です。
―更年期症状の研究は日々進んでいるのですね。ホットフラッシュの頻度で将来の慢性疾患のリスクが分かるかもしれないなど、大変興味深いお話でした。新しい情報をキャッチしていくことは大切ですね。今回も貴重なお話をありがとうございました。
※7 Archer 2011 Climacteric
※8 視床下部に局在する神経ペプチドの頭文字で、神経ペプチドを合成(分泌)する神経のこと。K: Kisspeptin(キスペプチン、KISS)、N: Neurokinin(ニューロキニン、NK)、Dy:Dynorphin(ダイノルフィン)
※9 Thurston 2018 Menopause
※10 Thurston 2023 Neurology
<この記事を監修いただいた先生>

寺内 公一 先生
東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 茨城県地域産科婦人科学講座 教授
▼詳しいプロフィールを見る
<インタビュアー>

満留 礼子
ライター、編集者。暮らしをテーマにした書籍、雑誌記事、広告の制作に携わる傍ら、更年期のヘルスケアについて医療・患者の間に立って考えるメノポーズカウンセラー(「NPO法人 更年期と加齢のヘルスケア」認定)の資格を取得。更年期に関する記事制作も多い。