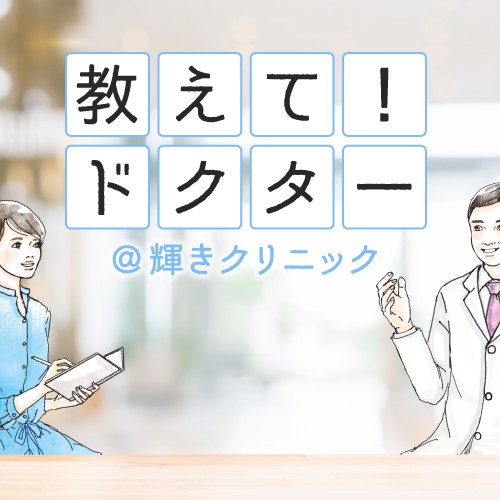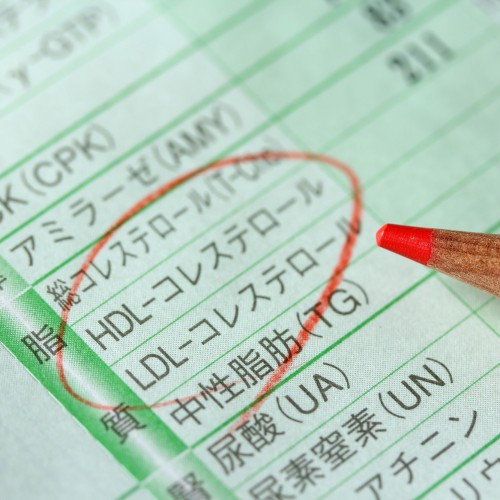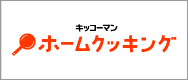更年期の頭痛(緊張型頭痛、片頭痛)の特徴は?症状や対処方法を分かりやすく解説
更新日: 公開日:
学ぶ
「更年期の頭痛がひどくて生活に支障がある」「少しでも頭痛を改善して普段どおりの生活を送りたい」。更年期世代の女性は、このようなことに悩んでいるのではないでしょうか。閉経にともなって卵巣の機能が低下する更年期になると、つらい頭痛に悩まされる女性が多い傾向にあります。
本記事では、更年期世代に頭痛が多い理由やその原因、更年期世代の頭痛の種類について解説しています。頭痛の具体的な予防法や対処法、頭痛に関するよくある質問についても回答しているため、更年期世代の方は参考にしてください。
更年期世代に頭痛が多い理由
更年期外来の患者を対象にした調査(※1)によると、週1回以上の頭痛がある人は半数以上、ほぼ毎日頭痛があるという人は約14%いると分かっています。
更年期の女性に頭痛が起こりやすい理由は、ライフサイクル上で過度なストレスがかかりやすいことが挙げられます。更年期の女性に多く見られる頭痛の原因は、抑うつの症状と関連があると分かっているためです。更年期で憂鬱な気分や抑うつ症状を自覚している女性は、頭痛にも悩まされる傾向にあるということです。
※1:Terauchi et al. Evid-Based Compl Alt 2014: 593560, 2014
更年期世代の頭痛の原因は女性ホルモンのゆらぎ
更年期の女性に現れる頭痛の症状は、閉経後に軽くなる傾向があります。そのため、更年期の頭痛は女性ホルモンのゆらぎが原因で起こると考えられています。そもそも更年期とは、女性ホルモン(エストロゲン)の分泌量が減っていくことで、さまざまな症状が現れる状態のことです。
エストロゲンの分泌量が低下すると女性ホルモンのゆらぎが起こり、神経の末端からカルシトニン遺伝子関連ペプチド(calcitonin gene-related peptide/CGRP)というタンパク質が放出されます。これによって血管が広がり、頭痛が起こってしまうというわけです。
更年期世代の頭痛の種類
更年期の女性に起こる頭痛は、片頭痛と緊張型頭痛の2種類に分類されます。両者をクリアに分けることは難しい場合もありますが、各症状の特徴についてご紹介しましょう。
片頭痛
頭の片側にズキンズキンと響くような痛みが起こるのが片頭痛の特徴です。先述したとおり、更年期による片頭痛は女性ホルモンのゆらぎによって起こると考えられています。片頭痛のなかには、「月経関連片頭痛」というものがあり、月経周期中に女性ホルモンの変動にともなって起こる片頭痛です。
片頭痛が起こるそのほかの原因として、睡眠不足・天候の変化・空腹・ストレス・感覚への過度な刺激なども挙げられます。身体活動や光・音・匂いによって症状が悪化することもあるほか、吐き気や嘔吐が引き起こされることも珍しくありません。
緊張型頭痛
緊張型頭痛の特徴は、頭をきつい帽子やベルトで締め付けられるような痛みが起こることです。緊張型頭痛はストレス・睡眠障害・肩こり・首の痛み・あごの痛み(顎関節症)・眼精疲労などが引き金で起こる傾向にあります。
ただし、緊張型頭痛と女性ホルモンとの関連はあまりないと考えられています。片頭痛とは異なり、身体活動や光・音・匂いによって痛みが悪化したり、吐き気や嘔吐が起こったりすることはありません。
※頭痛の裏に膜下出血や脳出血などの疾患が隠れている場合もあるため、症状が長引く場合や強い痛みを感じるときは、医師の診療を受けることを推奨します。
更年期の頭痛を予防・対処する方法

更年期の頭痛を予防・対処する方法として、以下のようなものがあります。
●薬物療法
●ホルモン補充療法(HRT)
●漢方療法
●食事療法
●補完代替医療
●こまめに筋肉を動かす
ここからは、それぞれの予防法・対処法について詳しく見ていきましょう。
薬物療法
更年期の片頭痛に対してピンポイントでアプローチできる方法として、トリプタン製剤による薬物療法が挙げられます。トリプタン製剤は片頭痛が起こり始めたときに服用することで、痛みの緩和・片頭痛発作時の吐き気・光や音に対する過敏などを改善する作用が期待できる薬です。
また、昨今では片頭痛の予防薬(注射)である「エムガルティ®」「アジョビ®」「アイモビーグ®」も登場しました。各薬によって治療法は異なりますが、基本的には月1回程度の注射で片頭痛が予防できます。
ホルモン補充療法(HRT)
ホルモン補充療法(HRT)とは、女性ホルモンのエストロゲンを補う治療法です。エストロゲン製剤を主として、場合により黄体ホルモン製剤も併用することで症状の緩和を目指します。
内服薬のほか皮膚に貼るタイプや塗るタイプの薬も登場しており、症状や希望に応じた処方が受けられます。
漢方療法
更年期に対する漢方療法では、「当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)」「加味逍遥散(かみしょうようさん)」「桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)」などが用いられます。
そのなかでも、頭痛がある場合は「当帰芍薬散」が処方されるのが一般的です。当帰芍薬散は、体力が弱く貧血気味で少しむくみがあり、頭痛やめまい、肩こりなどの症状がある方に処方されます。
食事療法
更年期による頭痛を予防する方法の一つとして、食事療法が挙げられます。食事療法では偏った食事を避けて、必要な栄養素をバランスよく摂ることが大切です。タンパク質やビタミン、ミネラルなど、栄養のある成分の摂取を心がけるとよいでしょう。
ただし年齢や体格、日常的に体を動かす頻度などによって適正な食事量は異なるため、詳しくは医師へ相談するようにしてください。
補完代替医療
補完代替医療とは、通常の西洋医学などを補う、または代わりの医療で補完することをいいます。更年期症状に対する補完代替医療としては、植物エストロゲンとも呼ばれる大豆イソフラボンを摂取することが挙げられます。大豆イソフラボンはホットフラッシュの頻度を減少させることが分かっており、注目されている成分の一つです。また、最近の研究において、ミドルエイジ女性の頭痛はイソフラボン摂取量と負の相関があることが報告されております(Kazama, Terauchi, Nutrients 2022, 14, 1226-1235)。
昨今では、「ブドウ種子ポリフェノール」などを摂取することによって、頭痛を含む更年期症状が改善することも報告されています。
まめに筋肉を動かす
こまめに筋肉を動かすことも、更年期による頭痛を予防する方法の一つとして効果的です。とくに緊張型頭痛は、首や肩のコリ・緊張が一因と考えられています。
首や肩への負担を軽減するためにも、肩を上げ下げしたり、腕や背中を伸ばしたり、同じ姿勢をとり続けないようにしたりすることも意識してみてください。
更年期の頭痛に関するよくある質問
ここからは、更年期の頭痛に関するよくある質問に回答していきます。
更年期の頭痛にはどのような特徴がありますか?
更年期に起こる頭痛の症状は人によって異なりますが、その多くは片頭痛または緊張型頭痛のどちらかであるといわれています。片頭痛の特徴は、頭の片側がズキンズキンと脈打つように痛むことで、女性ホルモンとの関連があるといわれています。一方の緊張型頭痛は、頭全体に締め付けられるような痛みが出ることが特徴で、女性ホルモンとの関連はあまりないといわれてます。
更年期の片頭痛はいつまで続きますか?
一般的に、緊張型頭痛は、閉経後も症状が起こる頻度が変わらないといわれ、片頭痛は、閉経後に症状が軽くなることが分かっています。
更年期の片頭痛の現れ方には個人差があるため、いつまでに落ち着くということは一概にはいえません。症状が軽い人もいれば、5年や10年など長期にわたって続く人もいます。
更年期の頭痛はどのように治せばいいですか?
更年期の頭痛の治療法としては、薬物療法やホルモン補充療法、漢方療法が効果的です。また頭痛を予防したい場合は、大豆イソフラボンを摂取することをおすすめします。
生活のバランスを整えて頭痛を予防しよう

女性ホルモンのゆらぎが原因で起こる更年期の片頭痛には、女性ホルモンを補う薬剤や漢方薬を服用する方法で治療を行うのが一般的です。しかし、食事療法や補完代替医療でケアすることも可能です。
とくに大豆イソフラボンを摂取することは、頭痛だけでなくホットフラッシュをはじめとする更年期症状を緩和・予防する効果が期待できます。頭痛が気になる方は、食生活を整えることも視野に入れてみましょう。
なお、毎日の食事で大豆イソフラボンを摂るのが難しいという場合は、サプリメントで補うという選択肢もあります。大豆イソフラボンのなかでもエストロゲンと同じような働きが期待できる「ゲニステイン」を配合したサプリメントもあるので、気になる方はぜひチェックしてください。
<この記事を監修いただいた先生>

寺内 公一 先生
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科茨城県地域産科婦人科学講座教授
▼詳しいプロフィールを見る